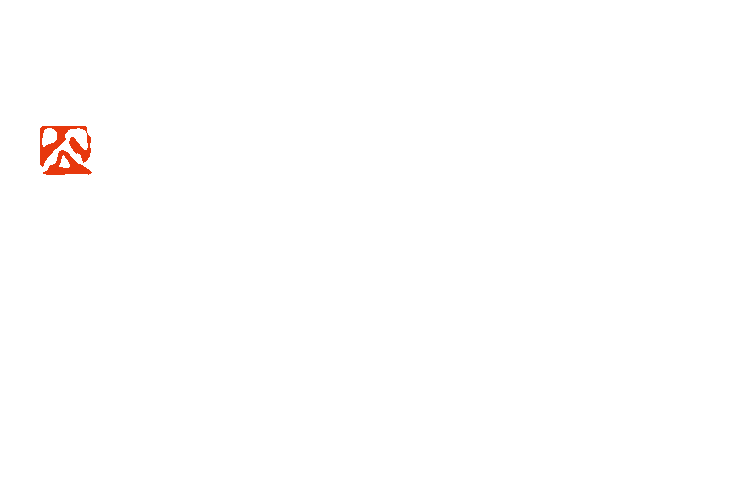こんにちは!奈良の郷土料理「柿の葉寿司」のゐざさ-中谷本舗-です!
早速ですが、節分と聞いて皆さんは何月を思い浮かべますか?
多くの方が2月をイメージされるのではないでしょうか。
でも実は本来、年4回あるのを知っていますか?
そもそも「節分」ってどういう行事かご存じですか?
今回は「なぜ節分が年4回もあるの?」「そもそも節分とは?」「恵方巻を節分に食べるのはなぜ?」といった疑問にお答えいたします♪
最後に、当社の恵方巻もご紹介します。そちらもチェックしてくださいね。
そもそも節分とは?
現代の私たちにとって、「節分」は2月の行事ですよね。でも、本来の節分の意味を考えると、「節分」は実は年4回あるんです。
「節分」とは、季節の節目である「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日のことを言います。漢字の通り「季節の分け目」の日という意味です。
その中でも旧暦では春から1年が始まるとされていたので、「立春」の前日である「春の節分」が大切とされ、今では冬から春にかわる節目のことが「節分」であるという認識が広まったのです。
節分といえば、2月3日のイメージが強いと思いますが、実は2月2日などにズレる年もあることをご存じでしょうか?
2021年の節分は124年ぶりに2月2日が節分となり、話題となりましたね!
春の節分は立春の前日でしたよね。立春は二十四節気の一つ。二十四節気は、太陽と地球の位置関係で決まり、それは少しずつズレていきます。
つまり、立春の日も実は年によって変わる可能性があるので、節分も2月3日で固定、ということでもないのですね。
節分に行う行事って何?
節分に行う行事と言えば、「豆まき」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?

ちなみに、季節の分かれ目、特に年が変わる「春の節分」には、邪気が入りやすいと考えられていました。そこで、1年間の平穏無事と邪気を祓う意味を込め、「追儺(ついな)」という行事が行われていたそうです。
元々は平安時代に宮中行事として、大晦日に行われていたそうですが、江戸時代ごろまでに実施されなくなります。一方で庶民には、節分に豆をまいて鬼を追い払い無病息災を祈る行事として追儺が広まり、いつしか、豆まきが節分の行事となったといいます。
2024年の節分はいつ?
節分が年4回あることはわかっていただけたかと思います。もちろん、春の節分は皆さんが豆まきなどをすると思いますが、夏の節分(暦としては立秋の前日)も近年は、恵方巻を食べることが多くなってきています。
では、2024年の「春」の節分はいつでしょう?
「春の節分」は2月2日(日)
です。
そうなんです、今年も2021年以来の2月2日が節分となります。
節分に食べるものって何?恵方巻の由来とは?
「豆まき」とともに、節分に欠かせないものといえば、「恵方巻」ではないでしょうか。

恵方巻は、その年の縁起の良い方角「恵方」を向いて巻寿司を丸かぶりすると願い事がかない、福を招くとされる食べ物です。
元々は関西地方で広まった風習ですが、その由来は実は定かではなく、いくつか説があります。
有力な説の一つが、大正時代~戦後にかけて、大阪の花街で節分に行われていた行事を起源とするものです。
当時、花街では商売人らが芸子たちと一緒にお座敷遊びをするときに、商売繁盛を願って巻寿司を食べていたそうです。名前も恵方巻と言わずに「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」などと言われていたといいます。
その後、1980年代後半に大手コンビニチェーンが「恵方巻」という名前を付けて大々的にPRしたところ、全国に広まったとされています。
ちなみに、恵方巻は福を逃がさないように無言で食べるのが正式な食べ方。巻寿司も素朴なものばかりでなく、お肉などを使ったものや、最近ではロールケーキの恵方巻など、色々な恵方巻が登場しています。
2025年の恵方は?どうやって決まっているの?
今年の恵方は「西南西」。
この恵方、どうやって決まっているか知っていますか?
「恵方」とは、その年の幸運を司る神様「歳徳神(としとくじん)」がいる場所(方角)を指します。歳徳神のいる場所は年によって変わります。
実は「恵方」は東北東、西南西、南南東、北北西の基本的に四つしかありません。それに、十干(じっかん)と呼ばれる暦を表示するのに用いられる十二支のようなものを組み合わせて、恵方の方角を決めるのです。
恵方巻の正しい食べ方!この3つを守れば完璧!
恵方巻には「食べ方のルール」があるのをご存じでしょうか?
「食べ方のルール」といってもそんなに難しくはありません!次の3つを守って食べることで、福を呼び込めるとされていますので、ぜひやってみてくださいね。
【その1】恵方巻は丸かぶりする!
食べやすいようにと、大きな恵方巻をカットすることもあると思いますが、ルールに則れば、それは間違い。
切らずにそのまま「丸かぶり」するのが本来の食べ方。元々、商売人たちが縁起をかついで食べていたものなので、「丸かぶり」して食べることで1年の幸福や商売繁盛の運を一気にいただく、という意味合いがあるようです。
【その2】恵方巻は黙って食べる!
恵方巻は1本を食べきるまで会話をしてはいけません。会話をすることで運が逃げると思われているからで、黙って今年1年の願い事を考えながら食べると良いとされています。
【その3】その年の恵方に向かって食べる!
上述したように、恵方巻は「恵方」を向いて食べることで、その年1年の福を呼び込むとされています。
上方伝統のゐざさの恵方巻
ゐざさでは、恵方巻のご予約は毎年12月25日前後に開始しています。少し甘めのシャリに、厚焼玉子や高野豆腐などを合わせた上方伝統の巻寿司です。
定番のゐざさの恵方巻3種類

恵方巻 ゐざさ巻
素朴な具材を巻き込んだ伝統的な巻寿司

恵方巻 上巻
あなごや高野豆腐、厚焼玉子などを巻き込んだひと品

恵方巻 特上巻
「海老」まで入った、風味豊かな恵方巻
※上記のリンク先は毎年12月25日前後に公開予定です。
「恵方巻 ゐざさの巻」のレビュー
嬉しいお声がたくさん寄せられています!ぜひ、お客様のお声を参考にしていただければ嬉しいです。
ご家族に人気!恵方巻詰合せ

素朴ながらも味わい深い、ゐざさの恵方巻を計8本詰合せた商品。
あなご、厚焼玉子、高野豆腐などが入った「上巻」、あなごの旨みが美味しい「あなご中巻」、えびが入った「えび中巻」。いずれも通常のハーフサイズ(長さ約9センチ)なので、お子様や女性にも食べやすい恵方巻です。
※上記のリンク先は毎年12月25日前後に公開予定です。
「恵方巻 詰合せ」のレビュー
ご家族用や、贈り物にも喜んでいただける「恵方巻 詰合せ」。この商品にもたくさんの嬉しいお声をいただいています。
忙しい方々に便利!事前に受け取れて当日チンするだけの冷凍恵方巻

お忙しい方におすすめ。受取期間が1月24日からなので、ご自宅にいらっしゃるときに事前受取りしていただき、節分当日に電子レンジで温めていただくだけでOK。「上巻」、「あなご巻」、脂の乗った鰻を使った「うなぎ巻」、甘辛い味付けが美味しい「黒毛和牛しぐれ煮巻」。いずれも食べやすいハーフサイズ(長さ約9センチ)を1本ずつ詰合せました。電子レンジで温めていただき、少し蒸らしていただくことでお召し上がりいただけます。
※上記のリンク先は毎年12月25日前後に公開予定です。
2025年の節分は恵方巻を食べて、福を呼び込もう!
邪気が入り込みやすい「節分」には、縁起の良い「恵方巻」を食べて福を招きましょう。
【今回のポイント】
・そもそも「節分」は「季節の変わり目」の意味。その中で立春の前日の節分が、1年の始まりということで重要視された。
・恵方巻は、元々関西の風習。由来は諸説あるが、大阪の花街で商売繁盛を願って食べられたのが始まり。
・1970年代以降、大阪の海苔問屋の組合や大手コンビニのPRによって全国に広まった。
・恵方巻の正しい食べ方は、①切らずに丸かぶりする、②黙って食べる、③恵方を向いて食べる。
ぜひ、今回の記事を参考にしながら、「ゐざさ」の恵方巻を丸かぶりしませんか?
節分が終わったらひな祭り!ひな祭りにちらし寿司を食べる理由などを紹介した記事もぜひご覧ください!

▼公式サイトはこちら▼